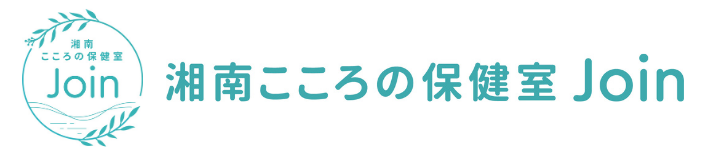前編では、「どう飲む?」という点について、最新の情報をご紹介しました。
後編では、「なぜ飲む?」に焦点を当てて、お酒とメンタルヘルスと人間関係について触れていきます。
お酒を飲む理由① メンタルに与える影響について
実はアルコールは「依存性薬物(ドラッグ)」
アルコールは、依存性薬物(ドラッグ)の一種です。
とても身近な存在なので、「薬物(ドラッグ)」という物々しい言葉に驚かれるかもしれません。
NPO法人ASKのウェブサイトでは、依存性薬物として、次のようなものを列挙しています。
アルコール 睡眠薬・抗不安薬 せきどめ薬 カフェイン 覚せい剤 大麻(マリファナ) ヘロイン LSD 合成薬物 コカイン シンナーやガスなど ニコチン
このように、アルコールは薬物の一種で、脳に直接働きかけ、体にも精神状態にも影響を与えます。
使うごとに耐性や依存性が生じるため、他の薬物と同じく付き合い方に注意が必要です。
アルコールは脳の働きをダウンさせ、リラックスや幸福感をもたらす
依存性薬物は、その作用の面から、大きく3つに分けられます。
| 分類 | 作用(はたらき) | 薬物の例 |
| 抑制(ダウナー) | 脳の働きをマヒさせる。 理性のコントロールがはずれてリラックスしたり、多幸感が得られるなど、「酔った」状態になる。 催眠(眠くなる)作用をともなうものも多い。 | アルコール 睡眠薬・抗不安薬 シンナー等 ニコチン 大麻(マリファナ) ヘロイン |
| 興奮(アッパー) | 脳を興奮させる。 いわゆる「ハイになった」状態。 | 覚せい剤 コカイン ニコチン |
| 幻覚 | 幻視・幻聴など、幻覚をもたらす。 | LSD シンナー等 合成薬物 |
このように、アルコールは脳の働きをダウンさせる薬物です。
お酒を飲むと、嫌なことやストレスを忘れてリラックスする効果が感じられるのは、このためです。
お酒がもたらす幸福感が、「依存」をもたらす
アルコールには、脳内に神経伝達物質であるドーパミン(快感や幸福感をもたらす)やセロトニン(不安を和らげる)を増やす作用があります。
ただし、その効果は始めの20分だけ、とも言われています。
その後は幸福感が減り不安が再来する(離脱する)ため、かえって抑うつ感が高まるのです。
また、飲酒が習慣化すると、脳の中にドーパミン等を回収する受容体が増え、前よりもたくさんのアルコールを取らないと快感が得られなくなっていくのです。これが「耐性」です。
あの快感と幸福感をもう一度得るためにと、どんどん酒量が増えていってしまう・・・これが「依存」に陥りやすい仕組みです。
依存には、お酒が無いと手が震える等の体の依存と、「またお酒を飲みたい」と考えてしまう精神依存があります。
薬を服用している人は注意! 飲酒との相乗リスク
このように、アルコールはれっきとした「薬」であり、体の中で様々な作用を起こします。
アルコールと他の薬の作用が重なると、効果がぶつかり合ったり、相乗効果で強く働いたりと、大変な影響が生じます。
肝臓による解毒が追いつかなくなると、深刻な症状が起きる場合もあるので注意しましょう。

お酒を飲む理由② 飲酒にまつわる人間関係について
飲みにケーションはもう古い? お酒は人との距離を縮める秘薬
お酒がもたらす理性の抑制と幸福感は、人付き合いをなめらかにし、人との距離感を縮めやすくすることがあります。
時代劇には武士が酒を酌み交わすシーンが出てきますが、人は昔から、お酒が仲間意識や連帯感をかもしだす効果を利用していたのかもしれません。

私自身は、育児で飲み会に参加しなくなった時、同僚や上司に相談できる機会が減ってしまい、飲み会が果たしていた役割を実感しました。お酒を頼りに職場の人間関係を築いていたと気付いたのです。
若者に限ったことではない? 周囲からの社会的圧力による飲酒
私は以前、保健室の先生として、子どもたちに向けて飲酒・喫煙・薬物乱用防止教育を行っていました。
大人になる前の若者が飲酒や喫煙を開始してしまう理由の大きな一つとして、「ピア・プレッシャー(仲間からのプレッシャー)」があると考えられています。

仲の良い友人や慕っている先輩から勧められたら、嫌われたくないという気持ちが働いて同調してしまう。

「怖いのか」「勇気がないな」「優等生だからな」などとあおられると、くやしくて応じてしまう。
そんな事例が多いため、どのように断ったら良いかという具体的なスキルについても指導していました。
けれど、周りからのプレッシャーで飲酒行動を取ってしまうのは、若者だけに限らないと思います。
お酒の席で、よく飲む人の方が周りから喜ばれ、歓迎されるように感じたことはありませんか?
もしその場が、会社や研究室など自分の進退が関わる重要なコミュニティであったら、気に入られたいと考えて無理にお酒を飲んでしまう場合があるかもしれません。
問題行動を支えていない? 周りの人はイネイブリングに注意
イネイブリング・イネイブラーとは
お酒を飲むことによって、体を壊したり、人に迷惑をかけたりする場合には「問題がある飲酒行動」と言えるでしょう。
ある人が問題飲酒を続けている時には、その周りの人が、問題飲酒を「可能にするように」「支えて」しまっている場合があります。支える行為を「イネイブリング」、支えている人のことを「イネイブラー」と呼びます。
例えば、以下のような行動はイネイブリングに該当します。
- 二日酔いで起きられない夫の代わりに、妻が会社に電話をして謝罪する
- 酔って散らかしたものや壊したものを、周りの人が片付ける
- 借金を肩代わりして返済する
責任の肩代わりをすると、本人が感じるべき後悔や痛みを軽減してしまうため、本人は嫌な思いをせずにすみます。その結果、「のど元過ぎれば」で、飲み続けることを可能にしてしまう悪循環になるのです。
家族、友人、同僚、上司など、本人のことを大切に思っている人ほどイネイブラーになりやすいです。
「私がなんとかしてあげなければ」という心配や善意が裏目に出る
悪循環が進む背景に、イネイブラーがアルコールに依存している人に対して、次の3つのコントロールをしてしまうことがあります。
- 飲酒行動をコントロールする(怒る、説教する、監視する、酒を隠す、捨てる、など)

- 飲酒の原因をコントロールする(機嫌をうかがう、ストレスを軽減する、生活を変えさせる、など)

- 飲酒の結果をコントロールする(介抱する、会社に言いわけをする、迷惑をかけた人に謝る、借金の肩代わりをする、など)
このようなイネイブラーになってしまう構造は、ギャンブル、買い物、ゲームなど、様々なものへの依存にも共通しています。
周囲がいくらやめさせようとしても失敗に終わり、最終的には本人のしたことの後始末に追われるようになってしまうのです。

イネイブリングの悪循環を断ち切ることが解決への第一歩
イネイブリングは、本人に対する愛情や好意、責任感から始まることが多く、そのこと自体は悪ではありません。
問題を起こしている人をコントロールしようとするのではなく、「私は心配だ」「治療を受けて欲しい」と「私」を主語にして話すと、気持ちが伝わりやすくなります。
イネイブリングをやめると本人は危機感を感じるので、イネイブラーを非難するなど一時的に状況が悪化したよう見えることがありますが、それが次へのステップにつながり、真の解決に向けた第一歩になるのです。
お酒と上手に付き合うためには? ストレス対処法のレパートリーを見直す
自分とお酒の付き合いについて振り返る、棚卸しのすすめ
いちど習慣になった行動は自分にとって当たり前になってしまい、特に理由もなく続けてしまうものです。
けれど、お酒を飲むことは、心と体の健康や人間関係など、人生の大切なことに関わる習慣です。
時には下のような問いについて考え、「自分とお酒の関係の棚卸し」をしてみてはいかがでしょうか?
・・・お酒を飲み始めた理由は、何?
- 人から勧められて?
- 美味しそうに飲む人を見てあこがれて? 等々
・・・今、お酒を飲む理由は何?
- ストレス解消?
- 周りの人と楽しい時間を過ごすため? 等々
・・・お酒を飲んで達成している↑のようなことに役立つ、他の方法はない?
ストレス対処法のレパートリーを増やそう

お酒はストレスを忘れさせて幸せな気分にしてくれる、便利なものです。
ただ、それはストレスや問題を「いったん棚上げにする」ことに役立つものの、「解決してくれる」ものではありません。
周りを気遣う優しい人ほど「自分さえ我慢すれば」「飲んで忘れればいい」と、お酒によるストレス対処に頼ってしまうリスクがあるかもしれません。
自分の心と体を守るために、ストレス対処法のレパートリーを少しずつ増やしていくようにできるといいですね。
Joinでは、ブログでの情報発信や、個別カウンセリングおよび講演会・研修会などの機会を通して、心の保健指導の活動を行っています。
ご意見、ご要望などありましたら、遠慮なくお問い合わせください。
※↓のお問い合わせフォーム、または公式LINEからご連絡ください。
〈出典〉
薬物乱用 いま、何を、どう伝えるか 水谷修著 大修館書店 2001
ドラッグなんていらない 出会ってしまう前のきみに伝えたいこと 水谷修著 東山書房 2004
アルコール・薬物・その他の依存問題を予防し、回復を応援する社会を作るNPO法人「ASK(アスク)」の情報発信サイト
https://www.ask.or.jp/article/644
プレジデントオンライン「酒を飲んでいるときだけは楽しい」のは危険信号…アルコール依存の人の脳内で起きている危険な反応とは お酒は快楽物質を得る”コスパ最強”の手段 垣渕 洋一東京アルコール医療総合センター・センター長の記事
https://president.jp/articles/-/70890?page=1
アルコール依存症治療ナビ
HELC 疾患・特集 お酒を飲むと楽しくなるのはなぜ?脳とアルコールのメカニズム
https://www.health.ne.jp/library/detail?slug=hcl_3000_w3000753