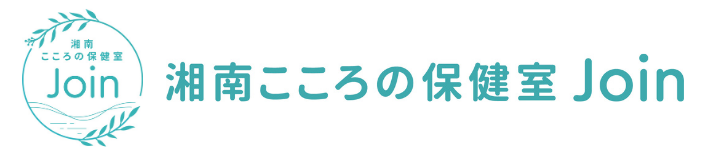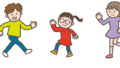わが子の不登校は、親も不安
子どもが学校へ行かなくなった時、動揺してしまう方は多いと思います。

- 心配で眠れない
- 「今日はどうなる?」と毎朝オロオロする
- ネットで情報を探し続ける
- 叱るべきか認めるべきか、対応に迷う
- 思うようにならないわが子にイライラする
- 元気なよその子と比べて悲しくなる・・・
こんな風に悩み、心を痛めている方のお話をたくさんお聞きしています。
そして、私自身も同じ思いを経験した一人でもあります。
子どもの不登校で生じやすい5つの悩み
休ませる?励まして登校させる?・・・親としての対応に迷う
子どもが「学校を休みたい」と行った時には、

「そう、わかった」と休ませる?
「行ってみよう」と背中を押す?
・・・と、とても迷うものです。
「本人の意思を尊重したい」と思いやる気持ちと。
「でも行ってみたら意外と平気と思えて学校に慣れるかも」と期待する気持ちと。
親も、気持ちが揺れてしまうことがあります。
叱らないわけにもいかず・・・親子関係が悪化する
学校に行かないので、家で子どもの姿を目にする機会が増えます。
大体の子どもはエネルギーを使い果たしてしまって休み始めるので、親から見るとネガティブな状態に見えやすいと思われます。
以下は、不登校の子どもに起こりやすい状態です。
- 遅寝、遅起きになる
- 少食、過食、偏食になる
- 入浴や歯磨きをしなくなる
- 寝転んでばかりいる
- ゲーム、動画、SNS、テレビなど、メディアを視聴する時間が増える
- 部屋が散らかる
- 外出や人目を避ける
子どもの身体はエネルギー回復のために自律神経系をオフ・モードにしていると考えると、上記の状態はごく自然なことです。
でもこのような姿は、親の目には「不健康」「怠けている」と感じられやすく、悲しく残念な気持ちになる方が多いようです。
そして「以前のように元気になってほしい」と願って、アドバイスや提案をしたくなります。
けれど、子どもは簡単には動いてくれません。(動けないのかもしれません)
そのうち、親が意見すると子どもは怒って言い争うようになり、親子関係が悪化する場合があります。
そして、子どもが親との会話を避けるようになると、何を考えているのかわからず、親はますます不安になってしまうのです。
何がいけなかったのか・・・誰か、そして自分を責めてしまう
何か問題が起きた時に原因を見つけて取り除こうとすることは、多くの方が行う対処法です。
けれど・・・

先生の対応?
お友だちとのトラブル?
夫が厳しすぎた?
自分が干渉しすぎた?
祖父母が甘やかしすぎた?
…と、原因が気になって、自分や誰かを責める思いが頭から離れなくなることがあります。
責める思いが言葉や行動に表れると、夫婦、親族、ご近所などとの関係が悪くなってしまうこともあります。
この先どうなる?・・・進路や将来が見えない不安がうずまく
文部科学省の統計によると、令和5年(2023年)度の不登校児童生徒数は約34万6千人で、全体の3.7%でした。
27人に1人が不登校であったと言えます。
しかし、1991年には不登校の児童生徒数は6万6千人で、全体の0.47%、212人に1人でした。
約30年前には不登校の子どもは、今よりも珍しい存在だったと言えるでしょう。
親世代が子どもの頃には不登校が今ほど身近ではなかったので、どのような進路で自立していくのかイメージが描けない方が多いのではないでしょうか。
人は、先の見通しがもてないと不安になるものです。
子どもに説得したり、ごほうびを提案したり、イライラして怒ったりしてしまう背景には、親自身の不安を解消したいという思いもあるのかもしれません。

親に反発できる子は、そうやって自分の心の健康を保とうとしているように見えます。
「親を悲しませたくない」「自分がもっと頑張らなくては」と思う、優しい子やまじめな子が、がまんを重ねて心身の不調を抱えてしまうことがあります。
親は、良かれと思ってわが子を導こうとするものです。
でもそれは、別の角度から見ると、子ども自身が将来や進路のことを自分ごととして考え、選びとる機会を妨げてしまう場合があるかもしれません。
子どもの人生の選択を本人に任せ、親は自分自身の不安に向き合い対処していく・・・そんな試練を迫られているように思われます。
知人と普通に話せない・・・親も人を避けてしまう
周りの人にわが子の現状をどう話すのか、話さないのか、という悩みも生じます。

知り合い程度の人に話して変に気を遣われるのは居心地が悪い
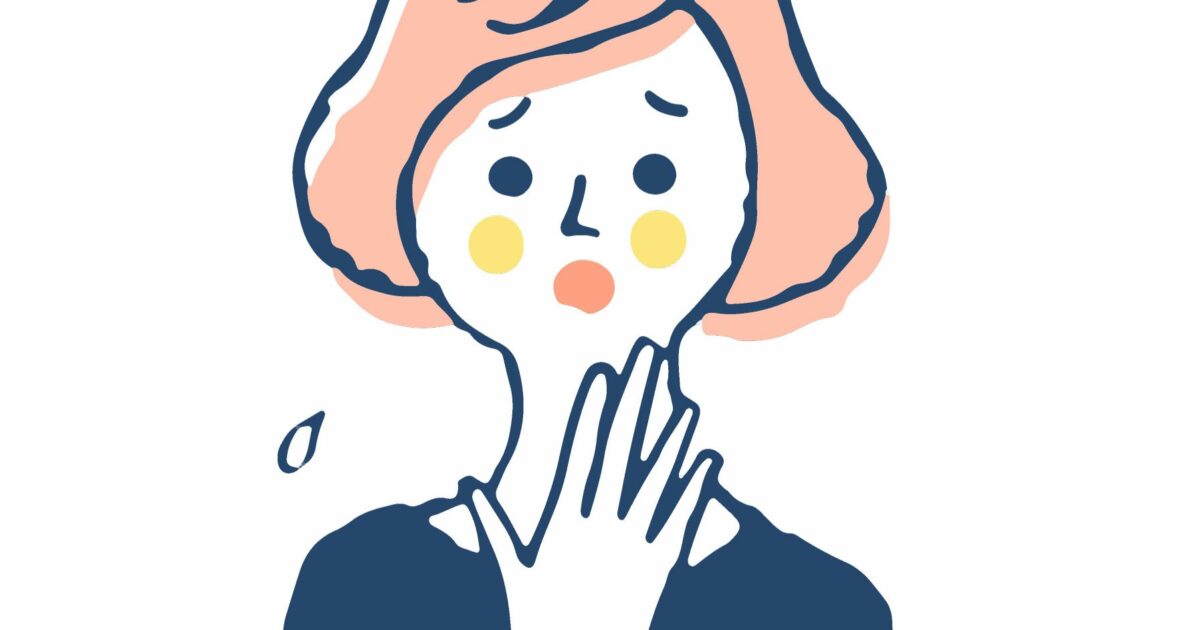
でも適当に話を合わせていると、嘘をついているようで後ろめたい
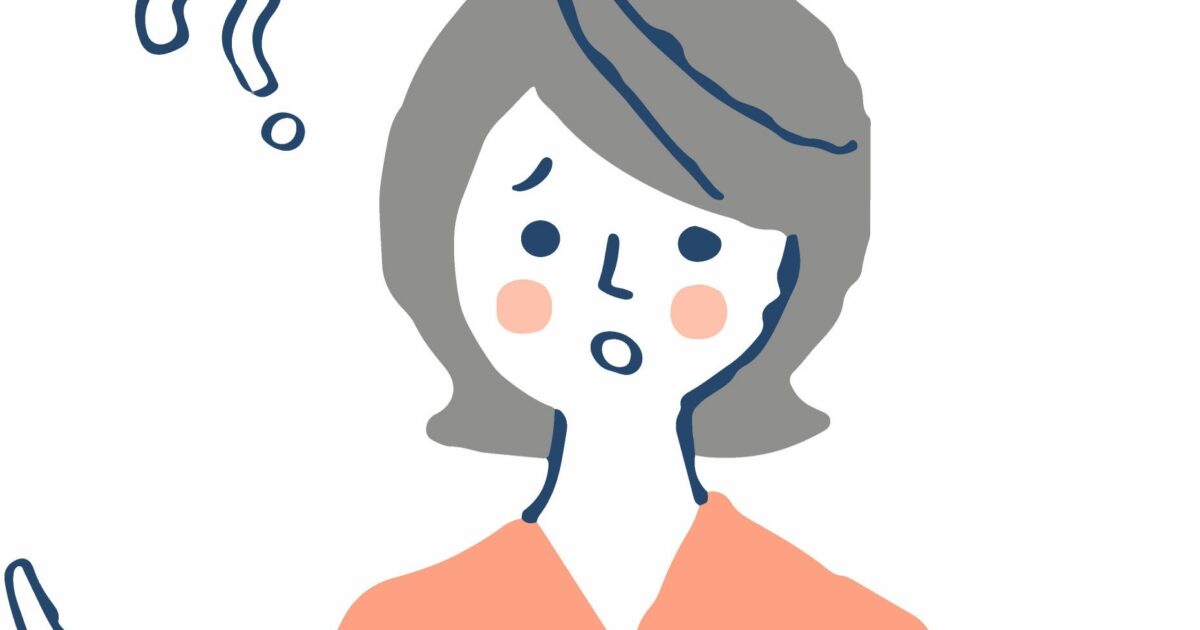
実家の親は「引きずって連れて行け」と言うけれど、私はそんなことしたくない…
このような家族以外の人への対応も、親にとって強いストレスになることがあります。
感情を揺さぶられて疲れてしまうので、なるべく会わないようにと、親も引きこもりがちになることもあります。
このような悩みを抱えてしまったら、どうすればいい?
身近な人への相談だけでは、解決が難しい場合も
子どもの不登校にまつわる親の悩みの特徴に、これまでの対処法が通用せず、悩みを解消しづらいという点があるのではないかと考えます。
ふつうの悩みであれば、家族、親戚、友人など、周りの人に相談してアドバイスをもらったり、グチを言って息抜きしたりして、なんとかなっている方が多いと思います。
けれど子どもの不登校となると、話が違ってきます。
人によって情報の量や質、価値観などが異なるため、周囲のアドバイスが「責め」に聞こえたり、腑に落ちずにモヤモヤを抱えたり・・・。
周りの人々と良い関係で協力することが難しくなるケースが多いように感じます。
近くの専門家とつながることがおすすめです
そんな時には、第三者に相談することをおすすめします。
学校の担任や学年主任の先生とは、やりとりがあることが多いと思います。
その次につながる先を、以下のような目安で選ぶと良いでしょう。
①お子さんがときどき学校に行くことがある場合
→スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育相談コーディネーターなど、学校にいる相談スタッフ
②学校への拒否が強いなど、まったく学校へ行くことがない場合
→教育センターや教育研究所など自治体の相談機関にいる心理士、ケースワーカーなどの相談スタッフ
子どもが直接相談に行かれなくても、親が相談につながることで、対応方法を落ち着いて考える手助けをしてもらえます。地域で利用できるサービスの情報などを教えてもらえる場合もあります。

プラスαの対応をお求めの方への選択肢
上記の①②を利用した上で、もう一歩先の対応が必要と思われる方は、医療機関やカウンセリングルームなどを探されるようです。
「湘南こころの保健室Join」もそのひとつで、プラスαの対応をお求めの方のご利用が多いです。例えば、以下のような理由でご相談に来る方が多いです。
- ①②では子どもへの対応について相談しているが、親自身のプライベートな悩みを話せる場所も欲しい
- 子どもへの対応方法について夫婦で意見が分かれているので、週末に夫婦で一緒にカウンセリングを受けたい
- 親として望ましい子どもとのコミュニケーション方法を教わって身につけたい
- ①②に通いつつも、セカンドオピニオンを聞きたい
- ①②には定期的に通っているが、急なことがあって混乱した時にスポット利用したい
- 強いストレスやトラウマへのケアを受けたい など
またJoinでは、屋号が表すとおり『つながりを作る』ことを大切にしています。
どことつながればよいかわからない方を必要なサービスにつなぐ支援も行っています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは→こちら
≪出典≫
文部科学省 令和6年10月31日発表 令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要
https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf